ゲーム理論とは?!簡単にご紹介?!お仕事でも利用できますがデメリットには要注意です?!
聞き流し用動画
はじめに
「ゲーム理論」という言葉を耳にした事はないでしょうか?
「ゲーム理論」については後ほどご紹介いたしますが、お仕事に活かす事ができる考え方となっています。
今回は「ゲーム理論」について触れたいと思います。
「ゲーム理論」を知り、お仕事の提案や戦略立案にお役立て頂きたいと思います。
ゲーム理論とは
「ゲーム理論」とは「お互いに影響を与える複数の意思決定者が存在する状況において、各意思決定者が最適な戦略を選択する為の理論」となります。
この理論は「経済学」「社会学」「政治学」「生物学」などのさまざまな分野の分析で応用されています。
「ゲーム理論」は、「競争や協力のような異なる相互作用の形態」を分析し、各意思決定者が「最良の選択をする為にはどのような戦略が存在するのか?」を分析します。
主な要素は「各意思決定者」「戦略」「報酬や利得」となります。
「代表的なゲーム理論の例」としては「囚人のジレンマ」があります。
これは「協力する事が最も合理的な選択であるにもかかわらず、お互いに裏切る事の方が個別の利益が得られる」というジレンマを扱っています。
「ゲーム理論」は「戦略的な意思決定」と「相互作用に関する理解」を深めます。
それでは分析の流れとなります。
「ゲーム理論の分析」は、「異なる意思決定者がお互いに影響し合う状況」をモデル化し、「最適な戦略」を見つける流れとなります。
「ゲーム理論の分析の基本的なステップ」をご紹介します。
- ゲームの定義
- 戦略の列挙
- 利得行列の作成
- ナッシュ均衡の探索
- 戦略的思考
- 分析の評価
- 分析結果の解釈と応用
ゲームの定義
最初のステップは、「対象となるゲームを明確に定義する事」となります。
この時、前述の「各意思決定者」「戦略」「報酬や利得」が「明確に定義する主な要素」となります。
戦略の列挙
「各意思決定者」がとれる可能な戦略を列挙します。
これにより「ゲームの戦略的な構造」を理解する事ができます。
利得行列の作成
「利得行列」とは「各意思決定者の異なる戦略の組み合わせに対する報酬や利得を示した表」となります。
「利得行列」を作る事により、「各戦略に対する各意思決定者の報酬や利得」を示す事ができます。
ナッシュ均衡の探索
「ナッシュ均衡(キンコウ)」とは「各意思決定者が相手の戦略を知りつつ、自分の戦略を変更せずにいられる状態」となります。
「ナッシュ均衡」を見つける事は、「ゲームの安定した状態」を理解する上で重要となります。
戦略的思考
「各意思決定者が最善の報酬や利得を得る」為に「自分がどの戦略を選択するのか?、また相手はどの戦略を選択するのか?を思考する事」となります。
これには「相手の戦略を予測する能力」や「自分の行動が相手に与える影響」を理解する事が重要となります。
分析の評価
「複数の均衡」や「複数の戦略」がある場合、それらを評価して「最適な物」を選択します。
これが「分析結果」となります。
この「最適な物」には「効率性」や「安定性」も考慮する必要があります。
分析結果の解釈と応用
「分析の結果」は、他のケースでも「実際の状況が一致する場合、応用する事が可能」となります。
これを体系化する事で「ビジネス戦略や競争戦略の最適化」が可能となります。
以上、「ゲーム理論の分析の基本的なステップ」となります
ゲーム理論の分析を通じて、異なる「各意思決定者が影響し合う複雑な状況に対する理解」を深め、「最適な戦略」を導き出す事が可能となります。
とはいえ、「デメリット」もあります。
「ゲーム理論の分析のおもなデメリット」をご紹介します。
- 情報の不完全性
- 合理的な行動仮定
- 思考の複雑性
- 均衡の多様性
- 時間の非同期性
- 協力の難しさ
情報の不完全性
「ゲーム理論」では「各意思決定者が相手の情報を完全に知っている」と仮定しています。
しかし、実際は「情報が不完全」な場合が多く、これが「正確な分析を難しくする」事となります。
合理的な行動仮定
「ゲーム理論」では「各意思決定者が合理的に行動する」という仮定に基づいています。
しかし、実際の行動は「感情、誤った予測、誤解などに影響を受ける」事があり、仮定と実際の行動が大きく異なる場合があります。
思考の複雑性
「ゲーム理論」では「多くの意志決定者」が戦略に絡む場合、思考が複雑になる事があります。
その結果、分析が困難な場合もあります。
均衡の多様性
「ゲーム理論」では「均衡がひとつ」とは限りません。
複数の均衡が存在し、どれが「実際に発生するのか?」は「状況に依存する事」となります。
このため「解釈や予測」が難しくなる場合があります。
時間の非同期性
「ゲーム理論」では「すべての意志決定者が同時に行動する」と仮定しています。
しかし、実際の状況では「すべての意志決定者が同時に行動する」事はあり得ません。
これが「時間の非同期性」となります。
この「時間の非同期性」が考慮されないと正確な分析が難しくなる場合があります。
協力の難しさ
「ゲーム理論」では「競争や対立の状況」に焦点を当てています。
しかし、「協力関係が必要」な場合もあります。
「協力関係が必要」な場合、「報酬や利得の最大化の考慮」が難しくなります。
特に「長期的な協力関係」においては「信頼構築」が必要となります。
この「信頼構築」が「協力戦略の構築」を難しい物にしています。
以上、「ゲーム理論の分析のおもなデメリット」となります
「デメリット」はあるのですが、「ゲーム理論」は「戦略的な意思決定の理解や競争状況の分析」においては非常に有用となります。
「デメリット」を理解して、お仕事に「ゲーム理論」をお役立て頂きたいと思います。
お仕事で利用できるゲーム理論
「ゲーム理論」は前述のとおり、さまざまな分野で応用されています。
お仕事では「意思決定」や「戦略の最適化」に役立ちます。
「お仕事で利用できるゲーム理論の考え方」をご紹介します。
- 競争戦略の分析
- 価格競争
- 交渉戦略
- リソース割り当て
- 戦略的連携と提携
競争戦略の分析
競合他社や取引先との関係をゲームとして捉え、相手の動きに対する最適な戦略を考える事ができます。
これにより「市場シェアの拡大や競争優位性の確立に役立つ戦略」を見つけることが可能となります。
価格競争
他社との価格競争において、相手の価格変動に対して「どのように対応するか?」をゲーム理論で分析できます。
これにより「価格戦略の最適化や市場での収益最大化」が可能となります。
交渉戦略
取引や契約交渉において、相手との交渉プロセスをゲームとしてモデリングします。
これにより「相手の動きを予測し、最適な合意を導くための戦略の策定」が可能となります。
リソース割り当て
企業内の予算や人員などの効果的な割り当てをゲーム理論で考える事ができます。
これにより「最適なリソース分配を見つける」事が可能となります。
戦略的連携と提携
他社との提携や連携を検討する時、互いに影響を与える要素をゲーム理論でモデリングします。
これにより、「最適な提携戦略を見つける」事が可能となります。
以上、「お仕事で利用できるゲーム理論の考え方」となります
これらのゲーム理論の考え方は、「企業戦略」や「意思決定の構築」において、相手の行動や選択を予測し、最適な答えを導き出す為に役立ちます。
simacatより一言
「ゲーム理論」が分からなくても構いません。
しかし、お仕事をする上では「誰が」は必要となります。
そして、お仕事である以上、「儲け」や「得」を意識する必要があります。
この「誰が」が「各意思決定者」であり「プレーヤー」となります。
「儲け」や「得」が「報酬や利得」となります。
そして、「プレーヤー」が「報酬や利得」を得る方法が「戦略」となります。
「プレーヤー」が何もしなくても「報酬や利得」を得られる場合があります。
これが「ナッシュ均衡」となります。
これらを自分のお仕事にあてはめた時、「何かをした方が良いのか?」「何もしなくても良いのか?」を考える助けとなります。
「ゲーム理論」は難しいかも知れませんが、「意思決定者」「戦略」「報酬や利得」について意識をする事は誰にでもできます。
お仕事をおこなう時は、是非、意識をして頂きたいと思います。

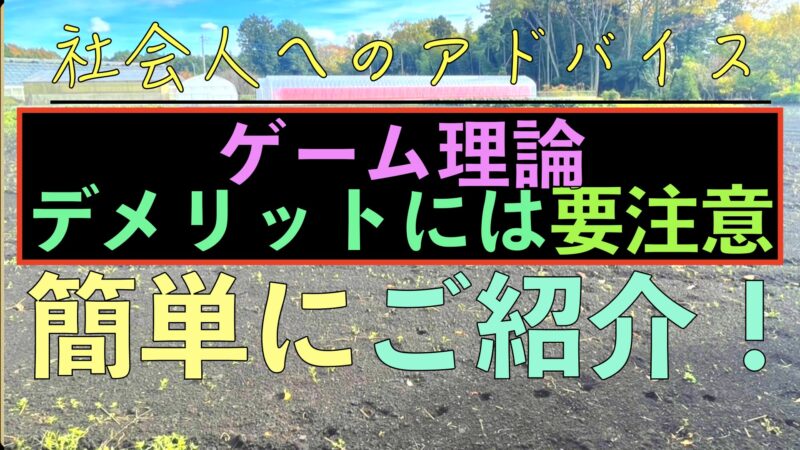

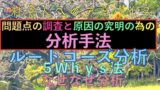

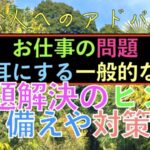

コメント