お仕事では危機回避能力が必要?!しかし「触れぬ、存ぜぬ、近寄らず」は危険です?!
聞き流し用動画(YouTube)
はじめに
普通にお仕事をしているだけなのに、同僚が怒られ、連帯責任と言われて自分も怒られる様な経験をした事はないでしょうか?
上司に余計な事を言ってしまった結果、上司の機嫌を損ねてしまった経験はないでしょうか?
お仕事をしていく上で「どうしてこうなった?」と思う事はたくさんあります。
「どうしてこうなった?」と思う事は、「想定をしていなかった」からとなります。
予め想定をして、回避ができれば、平和にお仕事を進める事ができます。
今回は「お仕事での危機回避能力」について触れたいと思います。
「危機回避能力」を「逃げる事」ではなく、「備え」としてお考え頂きたいと思います。
お仕事での危機回避能力とは
「お仕事での危機回避能力」についてとなります。
その前にそもそも「危機回避能力」とは、人間の本能による部分で、「命が危険にさらされる事を回避する」為に、「考えたり行動したりする能力」となります。
いまの世の中では「命が危険にさらされる機会」は非常に少なくなっています。
よって、人間の「危機回避能力」は低下していると言われています。
しかし、ほとんどの人はお仕事をして生計を立て、命を繋いでいる事を考えると、「お仕事を失敗する事」と「命が危険にさらされる事」とは、ほぼ同じ意味と言えます。
それでは「お仕事での危機回避能力」となります。
雰囲気を感じる
「お仕事がうまくいかない」「何をして良いのか分からない」、これらも「お仕事での危機」ではあるのですが、「危機回避能力」がなくても「お仕事が失敗する」事が想定できます。
「危機回避能力」とは、「具体的な原因や現象がないにも関わらず危機を感じ回避する能力」となります。
その為には「雰囲気を感じる」事が必要となります。
例えば、「職場の雰囲気」です。
お仕事をおこなう場所が職場となります。
この職場が「居ずらい状態」では、「緊張による思考停止」や「集中力の欠如」により、「お仕事が失敗する可能性」が高くなります。
よって、これも「お仕事での危機」となります。
「お仕事での危機回避能力」とは、この「雰囲気を察知し回避する事」となります。
「雰囲気を察知する」と言われても、「常に周りを警戒しなくてはいけないので難しい事」と考えます。
しかし、「いつもと同じ雰囲気」と「何かが違う雰囲気」であれば、認識する事ができます。
例えば「先輩や上司がソワソワしている」や「見知らぬ人がウロウロしている」などとなります。
また、「周りがいつもより賑やか」「周りが妙に静か」なども「感じ取る事ができる雰囲気」となります。
まずは、このような「雰囲気を感じとる事」が「お仕事での危機回避能力」の為には必要となります。
雰囲気を感じ取って何をするのか
次に「雰囲気を感じ取って何をするのか?」となりますが、これは「思考と行動」となります。
「いつもと違う雰囲気」を感じた時、「この違う雰囲気は自分にとって良い事なのか、悪い事なのか」を考える必要があります。
「自分にとって良い事」ならば、特に行動を起こす必要はありません。
しかし「自分にとって悪い事」ならば、行動をする必要があります。
これが「回避」となります。
「その場から離れる事」が一番良いのですが、お仕事をしているので席を外すのが難しい場合もあります。
その場合は、「考える能力」を「危機回避」に切り替えてください。
「危機回避」に切り替える事で、お仕事に集中する事ができなくなりますが、「いつ、誰が、何をして来ても良いように備えておく事」ができます。
そして、何事もなければ「考える能力」に戻り、お仕事に集中をするようにしてください。
雰囲気の印象と行動パターンを記憶する
忘れてはいけないのが、「危機と感じた雰囲気の印象と行動パターンを記憶しておく事」となります。
一度感じた「雰囲気の違い」から、思考や行動をおこない「回避」ができた時、その「雰囲気の違い」は「回避が可能な雰囲気」となる為、「危機」ではなくなります。
しかし、「回避できなかった時」は、危機に直面してしまい、「やり過ごす事」しかできません。
辛い思いをするかも知れませんが、その「やり過ごした行動」が「危機から脱する為の行動」となります。
同じような「危機に対する行動をパターンとして記憶する」事で「今後」に活かす事ができます。
人に対する雰囲気
「いろいろな雰囲気」を感じ取れるようになると、「人」に対しても、「雰囲気を感じる」事ができるようになります。
これは「自分が何を言っても伝わらない人に対して、どのように行動をするのか?」「自分に対して理解のある人に、どのように行動をするのか?」となります。
言い換えると「危険な人と安全な人の切り分け」です。
また「自分より上の人」、もしくは「自分より下の人」に対する行動についても同様です。
雰囲気を感じ取り、自分の取るべき行動パターンを決めておく事により、「危機」に直面した時に行動が取れるように備える事ができます。
以上、「お仕事での危機回避能力」でした。
もちろん、「知識や技術の向上」も「危機回避」には必要となります。
したがって、「知識や技術」について不安を感じるならば、「向上させる行動をする事」が「危機回避能力の向上」にもつながります。
お仕事での危機回避能力の問題点
強すぎる「お仕事での危機回避能力」には問題があります。
触れぬ、存ぜぬ、近寄らず
究極の「危機回避」は、「触れぬ、存ぜぬ、近寄らず」となります。
触らなければ何も起こりません。
知らなければ何もする事ができません。
近寄らなければ「危機」に直面する事はありません。
しかし、これではお仕事になりません。
お仕事をする以上、お仕事はしなくてはいけませんし、お仕事を知らなくてはいけませんし、職場にも行かなくてはいけません。
したがって、お仕事をする以上、時には「危機的状態」になる事も必要となります。
逆に、この「危機的状態」を体験しないと「危機回避能力を向上させる事ができない」と考えるようにしてください。
「危機回避能力が高い」と言う事は、「失敗という経験ができない」事となります。
「失敗は人間を強くする要素」で、「学ぶ事」が多くあります。
この「失敗」が足りない成長では、人として未熟な部分が残ってしまう為となります。
しかし、「失敗」により、「命を落とす」事があるのも事実です。
したがって、「命に関わらない程度の怪我は人の成長には必要な事」となります。
そして、「命に関わらない程度の怪我なのか?」を判断する能力も「危機回避能力」の一部となり、その為にも「危機的状態」を経験する必要があります。
simacatから一言
お仕事で「触れぬ、存ぜぬ、近寄らず」の人が一緒だと苦労をします。
自分からは何も行動をせず、行動を指示すると「なぜ自分がそんな事をしないといけないのか?」と怒り出します。
この様な人と接する事も、「危機回避能力」が高ければ回避できるかも知れません。
しかし、後輩や部下であるならば、このような考え方については、正しく指導をする必要があります。
誰でも、「危機」に対して不安はありますが、お仕事である以上、逃げてはいけない時もあります。
社会人としての多くの経験を積み「危機回避能力」を高めつつ、背負える範囲で「危険な事」と対峙して頂きたいと思います。

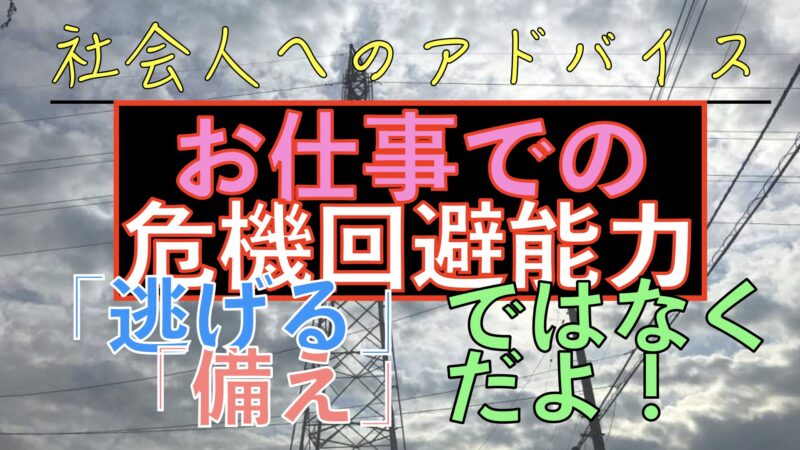







コメント